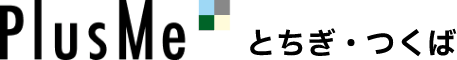大地震に備える家づくり、いまこそ耐震性を選ぶ理由
あなたの家族を守る安心の備えとして、耐震等級3を標準仕様に
地震大国・日本だからこそ、住まいの耐震性を見直す時期です。
『国土交通省白書2020』によると、今後起こりうる巨大地震のリスクとして、南海トラフ地震、首都直下地震があげられています。
南海トラフ地震では、静岡県から宮崎県にかけての一部では震度7となる可能性があるほか、それに隣接する周辺の広い地域では震度6強から6弱の強い揺れになると想定されています。
また、首都直下地震で想定されるマグニチュード7程度の地震の30年以内の発生確率は、70%程度(2020年1月24日時点)と予測されており、最大震度が7となる地域があるほか、広い地域で震度6強から6弱の強い揺れになると想定されています。
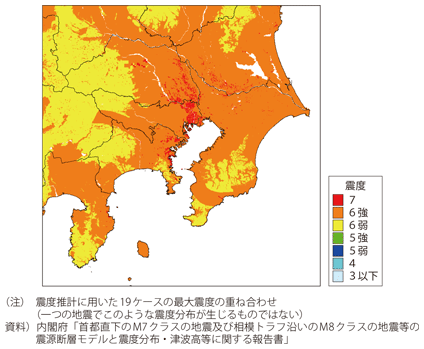
出典:「国土交通白書 2020」(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/r01/hakusho/r02/html/n1222000.html)(令和7年7月25日取得)
耐震等級について
耐震等級とは、住宅性能表示制度の一つ。建物が地震にどれだけ強いかを示す指標となっています。
等級には 1〜3 の三段階があり、数字が大きいほど耐震性能が高い建物となります。
◆住宅性能表示制度◆
2000年施行の「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づく指標

耐震等級3は、「建築基準法」で定められた耐震等級1の1.5倍の耐震性能を保持。
これは、震度6強から7程度の大地震にも耐えうる強度。消防署や警察署などの防災拠点と同等の耐震性が求められるレベルと同じです。
耐震等級3が求められる理由
大地震への高い耐性
2016年熊本地震では、耐震等級3の住宅の多くが大きな損傷が見られず、大部分が無被害であったことが報告されています。
出典:「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」報告書(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000633.html)(令和7年7月25日取得)
家族と財産を守る安全性
耐震等級3の住宅は、地震による倒壊や大きな損傷のリスクを大幅に低減できます。これにより、家族の命を守り、住宅内の財産や思い出も保護することができます。
災害後の生活の継続性
耐震等級3の住宅は、地震後も安全に居住を続けられる可能性が高いです。ですので、自宅での生活が継続でき、災害後の生活の質を維持しやすくなります。
メリット・デメリット
【メリット】
地震保険料の割引
耐震等級3の住宅は、地震保険料が最大で50%割引される場合があります。

注:保険料はご加入される保険会社ごとに異なります。割引率はご加入予定の保険会社にご確認下さい。
住宅ローンの金利優遇
耐震等級3の住宅は、住宅ローンの金利の優遇を受けられる場合があります。
【参考】
フラット35の場合https://www.flat35.com/index.html
資産価値の維持
耐震等級3の住宅は、第三者機関の認定を受けています。そのため、将来的な売却時にも高い評価を受けやすく、資産価値の維持につながります。
【デメリット】
建築コストの増加
構造計算や補強材使用等により、建築コストが増加する可能性があります。
プラスミーは全プラン耐震等級3仕様なので、材料コストは増加しません。
注:性能評価を受けるための申請費は別途かかります。
間取りの制約
耐震等級3を満たすためには、耐力壁の配置や柱・梁の強化が必要となります。そのことから、間取りの自由度が制限される場合があります。
プラスミーは構造の強さと使いやすさのバランスを考えたプランをご提案しています。
「耐震等級3相当」との違い
「耐震等級3相当」とは、公的な認定を受けていない独自認定の場合が多いです。ですので、地震保険の割引や住宅ローンの優遇措置は受けられません。
正式な「耐震等級3」の取得を目指すことが重要です。
プラスミーの耐震性
プラスミーは、全てのプランで、許容応力度計算を実施、耐震等級3を確保しています。余裕をもたせた構造設計で、「住み続けられる家」をご提供しています。

プラスミーが分かる「コンセプトブック」
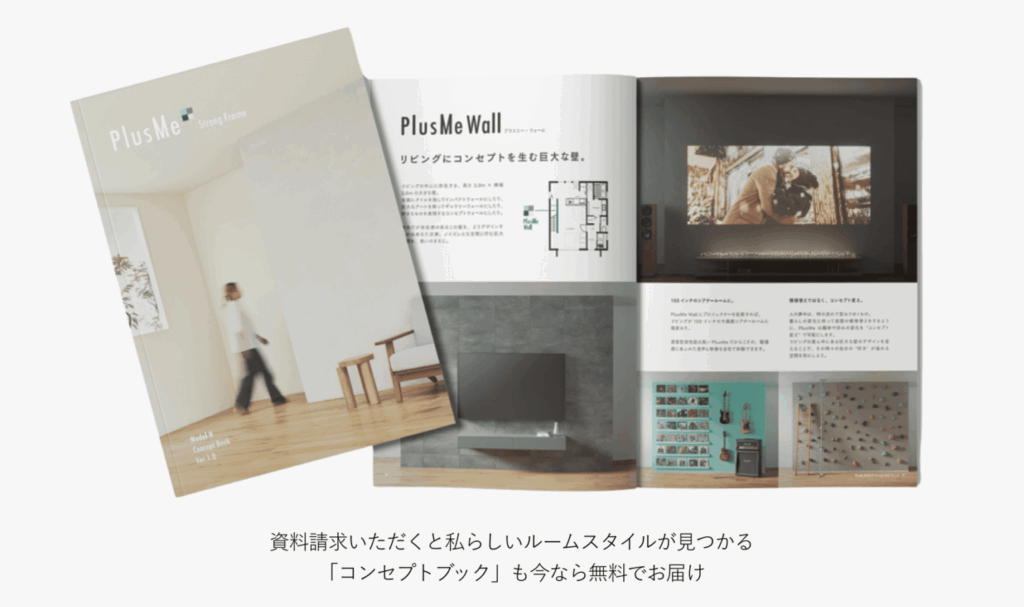
プラスミーが分かる「コンセプトブック」+プランシートを無料でお届け
その他の内容も下記フォームよりお気軽にご相談下さい。